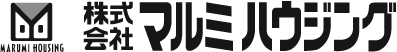ブログ
根抵当権が付いている不動産を相続した時はどうすればいい?
根抵当権についてお悩みの方はいらっしゃいませんか。
また、根抵当権という言葉を聞いたことがない方も多いでしょう。
今回はそんな方たちにむけて、根抵当権が付いている不動産を相続した時はどうすればいいのか、相続した不動産の根抵当権を維持する必要がない場合についてご説明します。
まず、根抵当権とは、貸し出すことのできる上限額を定め、その範囲のなかで多数の取引を一つにして担保できる抵当権です。
この上限額は担保となる不動産の価値から算出されます。
この根抵当権がついている不動産を相続した場合、基本的にはこの権利も相続されます。
しかし、根抵当権として相続するためには、相続してから6ヵ月以内に登記する必要があります。
この期間内に登記しなければ、根抵当権は抵当権になり、元本も確定します。
そのため、もし根抵当権がついている不動産を相続した場合は、まずその権利を相続するかどうかを考えましょう。
では、根抵当権のための手続きの流れについて説明します。
まず、その債権者である金融機関に連絡を取りましょう。
根抵当権を相続する場合はそこで書類を発行してもらう必要があります。
次に相続を放棄するかどうかを考えましょう。
相続することで不利益にならないかどうかきちんと調べておきましょう。
相続を放棄する場合は裁判所での手続きが必要です。
最後に根抵当権を相続することになった場合は登記手続きを行いましょう。
この手続きは6か月以内にする必要があります。
根抵当権を維持する必要がある場合は、被相続人の事業を引き継ぐ場合がほとんどです。
その場合、1つ目の手段として相続放棄があります。
相続放棄はすべての相続した財産の権利と義務を承継しない手続きのことです。
プラスの財産、マイナスの財産どちらもなくなります。
利益より不利益のほうが上回っているような場合は相続放棄をおすすめします。
2つ目の手段として根抵当権の抹消があります。
相続することを選択した場合、根抵当権に関する手続きを行う必要があります。
上記で示したように、事業の継承を行わない場合は、根抵当権のまま持つ必要はありません。
その場合は登記の手続きを行わずに根抵当権を抹消するようにしましょう。
今回は、根抵当権が付いている不動産を相続した時はどうすればいいのか、相続した不動産の根抵当権を維持する必要がない場合についてご説明しました。
根抵当権をそのままにするのかどうか、十分に考えましょう。
不動産の売買についてお悩みの方はぜひ当社までご相談ください。
また、根抵当権という言葉を聞いたことがない方も多いでしょう。
今回はそんな方たちにむけて、根抵当権が付いている不動産を相続した時はどうすればいいのか、相続した不動産の根抵当権を維持する必要がない場合についてご説明します。
□根抵当権が付いている不動産を相続した時にするべきこととは?
まず、根抵当権とは、貸し出すことのできる上限額を定め、その範囲のなかで多数の取引を一つにして担保できる抵当権です。
この上限額は担保となる不動産の価値から算出されます。
この根抵当権がついている不動産を相続した場合、基本的にはこの権利も相続されます。
しかし、根抵当権として相続するためには、相続してから6ヵ月以内に登記する必要があります。
この期間内に登記しなければ、根抵当権は抵当権になり、元本も確定します。
そのため、もし根抵当権がついている不動産を相続した場合は、まずその権利を相続するかどうかを考えましょう。
では、根抵当権のための手続きの流れについて説明します。
まず、その債権者である金融機関に連絡を取りましょう。
根抵当権を相続する場合はそこで書類を発行してもらう必要があります。
次に相続を放棄するかどうかを考えましょう。
相続することで不利益にならないかどうかきちんと調べておきましょう。
相続を放棄する場合は裁判所での手続きが必要です。
最後に根抵当権を相続することになった場合は登記手続きを行いましょう。
この手続きは6か月以内にする必要があります。
□根抵当権を維持する必要がないときにするべきことについて
根抵当権を維持する必要がある場合は、被相続人の事業を引き継ぐ場合がほとんどです。
その場合、1つ目の手段として相続放棄があります。
相続放棄はすべての相続した財産の権利と義務を承継しない手続きのことです。
プラスの財産、マイナスの財産どちらもなくなります。
利益より不利益のほうが上回っているような場合は相続放棄をおすすめします。
2つ目の手段として根抵当権の抹消があります。
相続することを選択した場合、根抵当権に関する手続きを行う必要があります。
上記で示したように、事業の継承を行わない場合は、根抵当権のまま持つ必要はありません。
その場合は登記の手続きを行わずに根抵当権を抹消するようにしましょう。
□まとめ
今回は、根抵当権が付いている不動産を相続した時はどうすればいいのか、相続した不動産の根抵当権を維持する必要がない場合についてご説明しました。
根抵当権をそのままにするのかどうか、十分に考えましょう。
不動産の売買についてお悩みの方はぜひ当社までご相談ください。